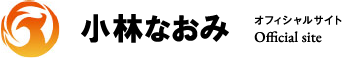みなさんも気になっているであろう、消費税減税。
今日はその消費税について、三橋貴明さんの解説をもとに、私、小林なおみがノートを取ってみました。
文章化することで、より皆さんも消費税の何が問題なのかが見えてくるのではないかと。。
三橋さんの解説動画のリンクも貼っておきますので、ぜひ併用してご覧になってみてください。
題して、<コバノート>←勝手に名前つけました😆
【三橋TV第934回】やっと減税が議論されているので「消費税」のウソを暴いておきます(私も騙されていました)
消費税法(納税義務者):
第五条 事業者は、国内において行った課税資産(財やサービス)の譲渡(取引)等(略)につき、この法律により消費税を納める義務がある
→納税義務者は消費者ではない
→消費税法には消費者という言葉が登場しない
では、(消費者が払っていると思い込まされている)消費税とは何か?:
→例)売価110円の水:税抜税込に関係なく、事業者が売価を110円にしているだけ。(100円に10円の税が乗っている水ではなく、単に売価が110円の水)
→「消費税は預かり金」説のウソ:免税事業者は消費税を預っているにもかかわらず納税してないのでおかしいという裁判があったが、財務省が説明し「消費税額は単に価格の一部を成しているに過ぎないので預り金ではない」という判決が出ている
→消費税は事業者の取引にかかる税金=取引税
→欧州では「付加価値税」:フランス政府が自国の輸出企業のルノーを助けるために導入された
消費税の仕組み:
課税売上から課税仕入れを引き、残りに税率をかけて計算する
→消費税 =(利益+非課税仕入)÷ 110 × 10
→非課税仕入のほとんどが給料(人件費)と社会保険料
→正規社員は人件費として非課税仕入になるが、外注による非正規雇用は課税仕入扱い
なので、企業にとっては消費税の節約ができる
↓
非正規雇用が増える(企業にとっては人件費や社会保険料の削減)
↓
雇用の不安定化と所得の低迷
↓
非婚化・少子化へ
直接税:税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(担税者あるいは納税義務者)が同一である税金
→所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税(ガソリン税)
※ただし、消費税以降は政府は間接税としている。。
間接税:税金を納める義務のある人と、税金を負担する人が異なる税金
→入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税
国民は【消費税】という名前に騙された!?日本での消費税導入の経緯:
・大平内閣が「一般消費税」という名前で導入しようとしたが失敗
・中曽根内閣が「売上税」で導入しようとしたが、企業経営者たちが法人税の上にさらに課税するのかと激怒し失敗
・竹下内閣が名前を「消費税」に戻して導入成功
消費税が導入されたり税率が上げられると。。
→政府の増収になる
→次の3者の誰かがその負担分を被る:価格据え置きで経営者(自社)か価格転嫁で消費者か、値下げ要求で仕入れ先か
→財務省:「消費税が増税された際事業者が価格に転化することが予定されている」??(「決定されている」や「法律で定められている」や「強制的にあげる」とは表現せずに「予定されている」と表現)
過去のキャンペーンポスターに見る消費税に関するプロパガンダ:
・「俺が払った消費税これっていわば預かり金なんだぜ」
・「消費税は預り金的性格を有する税です」
→明確に「預かり金」と言うことを避けている
疑問: 消費税が間接税で消費税分を事業者が預かりそれを納税する仕組みであれば、免税事業者があるのはおかしくないか?
・中小企業経営者にとっては消費税の税率が上がったからと言う理由でそのまま価格転嫁はできない
↓
消費税は減税し、インボイス制度は廃止